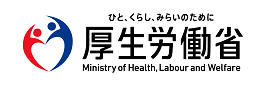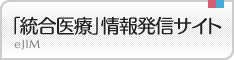オフィシャルブログ
- 2025.11.20
- アロマセラピー
アロマセラピーで心をととのえる:不安や落ち込みに寄り添う香りの選び方
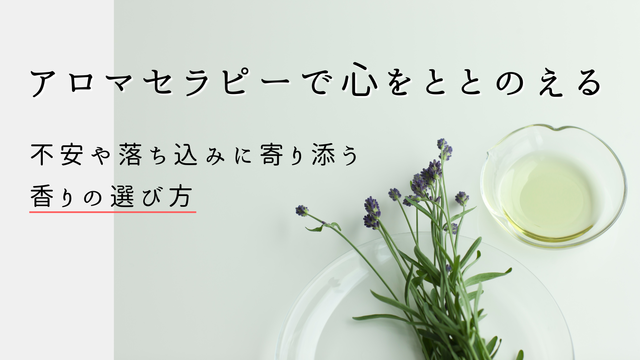
現代はストレスの入口が多すぎる時代。
仕事、人間関係、情報の洪水...。
頭では「休まなきゃ」とわかっていても、自律神経が追いつかず、不安や落ち込みを感じやすくなる人も少なくありません。
そんなとき、私たちの脳に最短距離で働きかけるのが香り。
アロマセラピーは、気分の揺らぎにそっと寄り添う、シンプルで続けやすいセルフケアの一つです。
ここでは「なぜ香りが心に作用するのか」という科学的背景から、日常での使い方、注意点まで、医学・心理学の視点を踏まえて深くわかりやすく解説します。
香りと心の関係
香りを感じる嗅覚は、五感の中で唯一、大脳辺縁系(感情を司る領域)にダイレクトに届くと言われています。
大脳辺縁系は
- 記憶
- 恐怖・不安などの情動
- 自律神経の働き
などを担う場所。
そのため、香りが脳に届くと、まず「感情」のスイッチが動き、次に「身体の反応」へと波及します。
これは他の感覚にはない特徴です。
心理学では、香りは以下のような効果をもたらすとされています。
- 緊張を緩める
- 呼吸を深くする
- 注意のベクトルを今ここに戻す
- イヤな記憶の再生を弱める
つまり、香りは「心 → 身体」「身体 → 心」の両方向から働きかける二重構造のケアと言えるのです。
不安を和らげる香りの種類
不安感が強いとき、脳は過剰に未来の危険を検索し続けます。
このとき役に立つのが、鎮静系の香調。
特徴としては
- 深い呼吸を誘導
- 自律神経の副交感を優位に
- 過剰な思考を減らす
などが挙げられます。
不安に寄り添う香りの分類例
- ハーバル系(草のような落ち着き)
思考のスピードをゆっくりにし、過剰な緊張をほどく香調。
- ウッディ系(木や森を感じる香り)
地に足をつけるグラウンディング効果。
恐れ・漠然とした不安に向いています。
- フローラル系(柔らかく包み込む香り)
心の硬さをゆるませる。
自責感が強いときに相性が良い香調。
どれが最適かは「体質」「香りの記憶」「生活背景」によって変わるため、数種類の香調を試し、安心感が戻る香りを1つ見つけておくのがおすすめです。
気持ちを前向きにする香りの種類
落ち込みや無気力が続くときは、脳の覚醒度が下がり停滞モードになりがちです。
ここでは活性系の香りが役立ちます。
前向きさを引き出す香りの特徴
- 思考をクリアにする
- 背筋がスッと伸びるような感覚
- ほんの少しドーパミン系を刺激し、「やってみよう」につながる
気分アップ系の分類例
- シトラス系(明るさ・軽やかさ)
脳への伝達が早く、気分転換に向いている。
- ミント系(クリアでシャキッとする香り)
ぼんやり感や停滞をリセットするのに適している。
- スパイス系(温かさのある刺激)
行動のアクセルになる香調。
あと一押ししたいときに。
ただし、落ち込みが深いときは、まず鎮静系で心を整えてから活性系を使うのがおすすめです。
ゆるめる → ととのえる → 引き上げると段階を踏むと安定が持続します。
日常に取り入れやすい活用法
アロマセラピーは特別な準備が不要で、ライフスタイルに合わせて選べるのが魅力です。
① 呼吸と合わせて使う
不安・緊張時は呼吸が浅くなるため、香りと呼吸法を組み合わせると相乗効果が生まれます。
鼻から4秒吸う → 香りを感じて2秒キープ → 6秒吐く、が基本。
② デスクに置ける点の使い方
ティッシュやコットンに少量を垂らして近くに置くなど、パーソナル空間だけを変える使い方は職場でも自然。
③ 就寝前の切替スイッチ
照明を落とし、鎮静系の香調を使うことで、1日の「終わりの儀式」になり、睡眠の質にも良い影響が出やすいとされています。
④ 朝の「気持ちの軸」をつくる
軽めの香調を使って1日のスタートを切ると、通勤・家事前のメンタルブレが減るという研究報告もあります。
アロマをセルフケアに活かすための注意点
香りは心身に優しいケアですが、いくつか押さえるべきポイントもあります。
香りの感じ方は記憶によって大きく変わる
同じ香調でも「懐かしい」「嫌な記憶が蘇る」など個人差が大きい。
必ず自分の感覚を基準にすること。
長時間の使用で逆に疲れることも
香りは刺激です。
集中を切り替えるときは数分単位のスポット使用が効果的。
心身の状態が不安定なときは弱めの刺激が基本
心理的負荷が高い日は、強い刺激の香調は逆効果になることがあります。
医療行為や治療の代替ではない
アロマセラピーはあくまでセルフケアの一手段。
不安・落ち込みが日常生活に支障をきたす場合は、専門機関のサポートを優先してください。
まとめ
アロマセラピーは「気分を変える」だけではなく、脳の感情領域に直接働きかけ、自律神経・呼吸・思考・行動に連鎖していく、非常に奥行きの深いメンタルケアです。
日常でストレスを抱えやすい現代だからこそ、自分の心にそっと手を添えるような「香りの使い方」を知っておくことは大きな安心感につながります。
香りはこころの伴走者。
あなたの生活の中に、小さな癒しの習慣として取り入れてみてください。
関連講座
クリニカルアロマインストラクター資格オンライン講座-日本統合医学協会-
通学コース
- 通学コース
- メディカルアロマセラピストコース
- メディカルヨガインストラクター養成コース
- メディカルピラティスインストラクター養成コース
- メディカルシニアヨガインストラクター養成コース
- オステオフレイルピラティスインストラクター養成コース
オンライン講座
協会について
日本統合医学協会は、東京と大阪に拠点を持ち、日本における健全な統合医学の普及と発展を目的として、平成12年に設立されました。メディカルアロマ、メディカルハーブ、またメディカルヨガやメディカルピラティスといった幅広い分野で技能研修や資格・検定の認定制度確立。統合医学の正しい知識の普及と技能向上に努めています。長年の実績と信頼ある当協会の資格は、医療・福祉の現場をはじめ、自宅サロン開業など転職・就職・開業にも役立てることが可能。統合医学の現場で働く皆様の活躍を後押しします。また、プロの育成だけでなく、セルフメディケーションとしてのメディカルアロマやメディカルヨガの普及にも注力し、誰もが「センテナリアン」を実現できる社会を目指し活動しています。