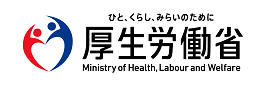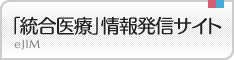オフィシャルブログ
- 2025.08.13
- ピラティス
フレイル・ロコモ・骨粗鬆症予防にピラティスが効く理由とは?
日本では平均寿命が世界トップレベルに達している一方で、健康寿命との差が大きな課題となっています。
特に高齢期に多く見られるフレイル(虚弱)、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)、骨粗鬆症は、いずれも転倒・骨折・寝たきりの大きな原因です。
これら3つは独立した症状ではなく、互いに密接に関連しています。
たとえば骨粗鬆症による骨折は、活動量低下を招き、筋力やバランス能力の低下(ロコモ)につながります。
さらに運動不足や社会参加の減少は、心身の活力を奪いフレイルを進行させます。
こうして「骨→筋→心身機能」の悪循環が生まれてしまうのです。
ピラティスが効果的な理由
この悪循環を断ち切るためには、骨・筋肉・神経系を同時に刺激し、全身機能を総合的に高める運動が求められます。
その条件を満たすのが、呼吸・姿勢・体幹の安定性を重視するピラティスです。
-
筋力とバランスを同時に強化
体幹深部の筋肉(インナーマッスル)を中心に鍛えることで、日常動作の安定性が向上し、転倒リスクを低減します。 -
骨密度の維持をサポート
自重を使った低衝撃運動が骨代謝を刺激し、骨粗鬆症予防に有効とされます。 -
呼吸と姿勢の改善
胸式呼吸で酸素摂取量を増やし、自律神経の安定や全身の代謝向上を促します。
フレイル・ロコモ・骨粗鬆症とは?3つの違いと共通点
加齢とともに心身の機能は少しずつ低下しますが、フレイル・ロコモ・骨粗鬆症は、その中でも特に健康寿命を縮めやすい3大要因です。
似ているようでいて、それぞれ定義や影響範囲が異なります。
フレイル(Frailty):心と体の虚弱状態
フレイルは、加齢や生活習慣によって身体機能・認知機能・精神面が総合的に弱っている状態を指します。
特徴は「健康」と「要介護」の中間に位置すること。
適切な介入で回復可能ですが、放置すると要介護状態に進行しやすくなります。
ロコモ(Locomotive Syndrome):運動器の機能低下
ロコモティブシンドロームは、骨・関節・筋肉など運動器の機能低下によって立つ・歩くといった基本動作が困難になる状態です。
原因は変形性関節症、脊椎疾患、サルコペニアなど多岐にわたり、進行すると転倒や骨折のリスクが高まります。
骨粗鬆症(Osteoporosis):骨の量と質の低下
骨粗鬆症は、骨密度と骨質の低下によって骨がもろくなり、軽い衝撃でも骨折しやすくなる病気です。
特に閉経後の女性や高齢者に多く、大腿骨や脊椎の骨折は寝たきりや要介護の原因となります。
3つの共通点と悪循環
-
共通点
いずれも加齢や運動不足、栄養不足が主な原因で、転倒・骨折・寝たきりのリスクを高める。
-
悪循環の例
骨粗鬆症で骨折 → 活動量低下 → 筋力低下(ロコモ) → 自立度・意欲低下(フレイル進行)
ポイント
3つは別々の病気や状態に見えますが、互いに影響し合う「連鎖反応」を起こします。
このため、予防は同時並行で行うことが理想です。
なぜピラティスがこれらの予防に効果的なのか?
フレイル・ロコモ・骨粗鬆症の予防には、既に述べた通り筋肉・骨・バランス機能を同時に鍛える運動が理想です。
ウォーキングや筋力トレーニングも有効ですが、これらは単一の効果に偏りがち。
一方、ピラティスは呼吸法と姿勢制御を組み合わせた全身運動であり、複数の効果を同時に得られる点が強みです。
-
筋力とバランス能力の同時強化(ロコモ予防)
ピラティスは体幹深部の筋肉(インナーマッスル)を鍛えながら、四肢の動きをコントロールします。
特に腹横筋・多裂筋・骨盤底筋など姿勢保持に重要な筋群を活性化させ、歩行や立ち上がり動作を安定させます。
これにより、転倒リスクを低減し、ロコモ予防に直結します。
エビデンス
高齢女性を対象とした研究で、週2回・12週間のピラティスがバランス能力を有意に改善(Cruz-Díaz et al., 2015)。
-
呼吸と姿勢の改善で全身機能を底上げ(フレイル予防)
ピラティス特有の胸式呼吸は、酸素摂取効率を高め、心肺機能をサポートします。
また、背骨の柔軟性を保つエクササイズは姿勢改善につながり、日常生活の活動意欲や自立度の維持に貢献します。
60歳以上の女性に週3回・8週間のピラティスを実施した研究では、下肢筋力・柔軟性・姿勢が有意に向上したという研究結果もあります。(Kim et al., 2014)。
また、精神的なリフレッシュ効果もあり、フレイル予防において重要な社会参加意欲の維持にも好影響を与えます。
ここまでお話してきましたが...ひとつ落とし穴が!
そう、骨粗鬆症に対しては注意が必要なのです。
そもそも従来のピラティスは骨粗鬆症予防を目的に設計された運動ではありません。
むしろ、骨粗鬆症の方が前屈や深い回旋動作を行うと、圧迫骨折や転倒のリスクが高まることが知られています。
このため、骨粗鬆症の人はピラティスの一部の動作が実施禁忌に分類されることもあります。
3.骨粗鬆症への応用は「安全設計」が前提
骨粗鬆症の予防や改善を目的にピラティスを行うには、動作の修正と安全性確保が不可欠です。
例えば、
- 背骨を大きく曲げる動作(前屈)は避ける
- 深い脊柱回旋やジャンプ動作を行わない
- 転倒リスクの少ない座位や仰臥位のエクササイズを中心にする
これらの工夫によって初めて、骨粗鬆症予防に応用可能になります。
そこで登場するのが「オステオフレイルピラティス®」
このプログラムは、整形外科医・理学療法士をはじめとする医療系多職種が共同で開発。
骨粗鬆症や人工関節置換後の方でも安全に行えるよう、禁忌動作を排除し、骨と筋肉の機能維持を目的に最適化されています。
その結果、フレイル・ロコモ予防だけでなく、骨粗鬆症に対してもリスクを抑えた形で取り組むことができます。
医師監修「オステオフレイルピラティス®」の特徴
ピラティスはリハビリ発祥の運動法ですが、骨粗鬆症の方にとっては一部の動きが骨折リスクを高める可能性があります。
そこで誕生したのが、整形外科医を中心に医療系多職種が共同開発した「オステオフレイルピラティス®」です。
このプログラムは、フレイル・ロコモ・骨粗鬆症予防を安全に同時進行で行えるように設計されており、現場での使用を前提に細部まで配慮が行き届いています。
-
医療系多職種による共同開発
整形外科医・理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士・ピラティストレーナーが連携し、科学的根拠と現場実践の両立を実現。
骨粗鬆症患者や人工関節置換後の方でも安心して実施できる内容になっています。
-
テキストに基づく安全設計
-
脊柱屈曲や深い回旋を伴う動作は除外
圧迫骨折や転倒のリスクを避けるため、背骨への負担が大きい前屈や急なねじりは行いません。
-
衝撃や不安定動作を避けたエクササイズ
ジャンプや急激な重心移動は排除し、安定姿勢での筋力・バランス強化に重点。
-
座位・仰臥位中心の構成
立位動作は応用編とし、初期は椅子やマット上で安全に実施。
-
段階的な負荷調整
体力や症状に合わせ、運動強度や可動域を細かく設定。
-
現場と家庭の両方で活用可能
医療・介護施設でのグループ体操やリハビリだけでなく、動画・テキスト教材を活用すれば自宅でも安全に継続可能。
これにより「施設で学ぶ → 家で続ける」という予防習慣の定着が期待できます。
日常生活での実践ポイント
ピラティスの効果を最大限に引き出すには、安全に・無理なく・継続的に行うことが大切です。
特に高齢者や骨粗鬆症の方は、自己流ではなく正しいフォームと負荷で行うことがポイントになります。
-
頻度と時間の目安
-
週2〜3回が理想的
体に刺激を与えつつ、回復時間も確保できます。
-
1回20〜30分を目安に
無理なく集中できる時間設定が継続のカギです。
-
痛みや違和感がある場合は中止
運動中に関節や腰に痛みを感じたら、すぐに中止して医師や理学療法士に相談しましょう。
「少しきついけど心地よい」程度の負荷が目安です。
-
呼吸を意識する
ピラティスは胸式呼吸を基本とします。
-
息を吸うとき
肋骨を横に広げるイメージ
-
息を吐くとき
お腹を引き締め、体幹を安定させる 呼吸と動作を連動させることで、筋肉の働きが最大化されます。
-
環境を整える
- 滑りにくいマットや安定した椅子を使用
- 床はフラットで周囲に障害物がない場所を選ぶ
- 室温や服装も快適に保つ
-
モチベーションを維持する工夫
- 動画教材やグループレッスンを活用
- 成果を日記やアプリに記録
- 家族や友人と一緒に取り組むことで継続率が向上
まとめ:ピラティスは「攻めの予防」の第一歩
フレイル・ロコモ・骨粗鬆症は、高齢者の健康寿命を縮める3大要因です。
一見別々の問題のようですが、筋力低下・骨密度低下・生活意欲の低下が互いに影響し合い、悪循環を生み出します。
その連鎖を断ち切るためには、筋肉・骨・神経系を同時に刺激できる運動が必要です。
ピラティスは、体幹を中心に全身を連動させる動きと呼吸法を組み合わせ、筋力・バランス力・骨密度・姿勢改善を一度にかなえる数少ない運動法です。
特に医師監修の「オステオフレイルピラティス®」は、安全性と効果を両立し、高齢者や骨粗鬆症の方でも安心して取り組めます。
今日から始められる予防習慣
- 週2〜3回、20分のピラティスを生活に取り入れる
- 無理のない動きからスタートし、少しずつ負荷を上げる
- 呼吸と姿勢を意識しながら行うことで効果アップ
結論
健康寿命を延ばすには、「いつかやろう」ではなく「今日からやる」ことが大切。
ピラティスは、フレイル・ロコモ・骨粗鬆症予防の攻めの第一歩になります。
未来の自分のために、今から一歩踏み出しましょう。
関連講座
通学コース
- 通学コース
- メディカルアロマセラピストコース
- メディカルヨガインストラクター養成コース
- メディカルピラティスインストラクター養成コース
- メディカルシニアヨガインストラクター養成コース
- オステオフレイルピラティスインストラクター養成コース
オンライン講座
協会について
日本統合医学協会は、東京と大阪に拠点を持ち、日本における健全な統合医学の普及と発展を目的として、平成12年に設立されました。メディカルアロマ、メディカルハーブ、またメディカルヨガやメディカルピラティスといった幅広い分野で技能研修や資格・検定の認定制度確立。統合医学の正しい知識の普及と技能向上に努めています。長年の実績と信頼ある当協会の資格は、医療・福祉の現場をはじめ、自宅サロン開業など転職・就職・開業にも役立てることが可能。統合医学の現場で働く皆様の活躍を後押しします。また、プロの育成だけでなく、セルフメディケーションとしてのメディカルアロマやメディカルヨガの普及にも注力し、誰もが「センテナリアン」を実現できる社会を目指し活動しています。