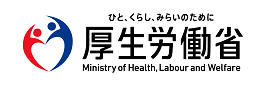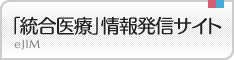オフィシャルブログ
- 2025.08.07
- ヨガ
ヨガインストラクターが見た体のSOS|働きすぎの人はなぜ前屈ができないのか?
ヨガのレッスンで、生徒からよく聞く言葉だ。
だが、長年ヨガを教えているあるインストラクターは、別の視点を持っていました。
「前屈できない人の多くは、ただ体が硬いのではなく、休めていないんです」
前屈とは、ただの柔軟性テストではない。
それは、現代人の心身の緊張を映し出す静かなバロメーターとも言えるのだ。
体が硬いのではなく、「交感神経が休まらない?!」
まず前提として、前屈動作では以下の要素が必要になる
- ハムストリングの伸張(太もも裏)
- 股関節の屈曲
- 背骨の屈曲(丸める動き)
- 腹部の弛緩
- 呼吸と連動する胸郭の可動性
どれも、力を抜く方向の動作だ。
だが、働きすぎて常に「交感神経優位(戦闘モード)」にある人の身体は、この抜くことが極端に苦手になっているとも考えられるのだ
緊張状態が筋肉をロックする
交感神経が優位になると、身体は常に臨戦態勢になる。
これは筋肉を硬直させ、微細な緊張状態が慢性化している状態だ。
特に、
- 腰背部(脊柱起立筋)
- ハムストリング
- ふくらはぎ
- 肩周囲
など、姿勢保持や逃走反応に関わる部位が過緊張になりやすい。
これは解剖学的にも自律神経支配の特徴と一致している。
結果として、前屈時に「曲がらない」「痛い」「呼吸が止まる」といった反応が出ると考えられる。
それは、単に柔軟性がないのではなく、脳が「今はゆるめるな」と指示を出している状態とも言える。
心の防御姿勢が、体を動かなくする
さらに興味深いのは、心理的な防衛反応が体の可動域に影響するという視点だ。
丸める動作は、自分をさらけ出す動作でもある
前屈とは、頭を下げ、体を小さく丸めていく動き。
言い換えれば、「緊張を手放し、自己を内省するポジション」とも捉えられる。
ヨガ哲学では、前屈のポーズ(パスチモッターナーサナなど)は「内観」と「謙虚さ」を表すとされる。
日常的に人前で気を張っている人、常に成果を求められている人にとって、この無防備な姿勢をとること自体が心理的ハードルになる可能性があるのだ。
実際に、多忙で責任感の強い人ほど、「前屈が怖い」「伸ばすと不安になる」といった感覚を訴えるケースもあるという。
働きすぎによるボディマッピングの歪み
また近年では、「ボディマッピング(身体感覚の脳内地図)」の歪みが柔軟性や可動性に影響するという研究も進んでいる。
働きすぎによって運動量が減り、一定の姿勢(例:パソコン作業)に偏った生活が続くと、極端な話、脳が「前屈の動作」そのものを忘れてしまう。
つまり、「できない」のではなく、「やり方を脳が思い出せない」という状態に陥る可能性もあるのだ。
前屈は緩める力のリトマス試験紙
こうした背景をふまえると、前屈は単なるストレッチではない。
それは、「いまの自分に、緩める余白があるかどうか」をチェックする行為と言えるかもしれない。
特に、以下のような人は前屈の中にヒントがあるかもしれない
- 休むと罪悪感を覚える
- 深呼吸が苦手
- 睡眠が浅く、頭が常にフル回転している
- 体が硬いのに、無理に伸ばそうとする癖がある
こうした緊張しっぱなしの生き方が、前屈で現れるのは偶然ではない可能性がある。
働きすぎの人にこそすすめたい脱力の前屈
では、どうすればよいのか。答えは、「伸ばさない前屈」だ。
Step 1|椅子の上で、お腹を太ももに預ける
椅子に浅く座り、背中を丸めてお腹を太ももに預ける。手はどこに置いても構わない。
重要なのは、「伸ばそうとしない」こと。
筋肉を伸ばすのではなく、「重力に体を任せる」ことで、神経の緊張をほどいていく。
Step 2|4秒吸って、8秒吐く呼吸
深い呼吸は副交感神経を優位にする。
特に「吐く息」を長く意識することで、脳が「もう戦わなくていい」と感じてくれる可能性がある。
3〜5呼吸だけでもいい。
少しずつ体の内側にスペースができる感覚を味わってみてほしい。
Step 3|夜のおやすみ前屈で脳をオフに
働きすぎで睡眠の質が落ちている人ほど、夜におすすめしたいのがおやすみ前屈。
ベッドの上に座り、クッションやブランケットを膝の上に置いて、そこに上半身を預けるように前屈する。
この姿勢は、安心感を脳に与え、副交感神経のスイッチを入れる助けになると考えられている。
結論|「前屈できない」という小さな異変にこそ、耳を澄ませて
体の硬さは、筋肉の問題だけではなく、心と神経の状態を映し出している身体の言語かもしれない。
前屈がうまくできないという感覚は、今のあなたにとって、もしかすると「もう少し立ち止まって休んでみては?」という静かなメッセージなのかもしれない。
ヨガは、がんばることではなく、「がんばらない練習」。
前屈の深さではなく、「ゆるめられるかどうか」こそが、現代人にとって最も必要な指標なのではないだろうか。
【関連講座】
通学コース
- 通学コース
- メディカルアロマセラピストコース
- メディカルヨガインストラクター養成コース
- メディカルピラティスインストラクター養成コース
- メディカルシニアヨガインストラクター養成コース
- オステオフレイルピラティスインストラクター養成コース
オンライン講座
協会について
日本統合医学協会は、東京と大阪に拠点を持ち、日本における健全な統合医学の普及と発展を目的として、平成12年に設立されました。メディカルアロマ、メディカルハーブ、またメディカルヨガやメディカルピラティスといった幅広い分野で技能研修や資格・検定の認定制度確立。統合医学の正しい知識の普及と技能向上に努めています。長年の実績と信頼ある当協会の資格は、医療・福祉の現場をはじめ、自宅サロン開業など転職・就職・開業にも役立てることが可能。統合医学の現場で働く皆様の活躍を後押しします。また、プロの育成だけでなく、セルフメディケーションとしてのメディカルアロマやメディカルヨガの普及にも注力し、誰もが「センテナリアン」を実現できる社会を目指し活動しています。